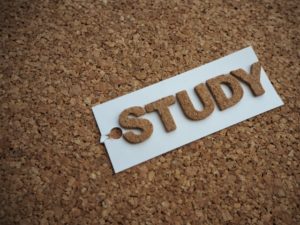こんにちは、ナナさんです。
このページにお越しいただきありがとうございます。
今回はFP試験を受けるきっかけになったかもしれない出来事について書きます。
夫の失業

結婚して1年経った頃に夫が失業しました。2馬力から1馬力になり困ったことがあります。
- 2馬力で膨らんでいる支出を抑えるのが大変
- 住民税、国民健康保険、国民年金を払うのが大変
住民税も国民健康保険も前年度の所得が基準になるので、納付書を見て「げっ!」。
国民健康保険と任意継続健康保険
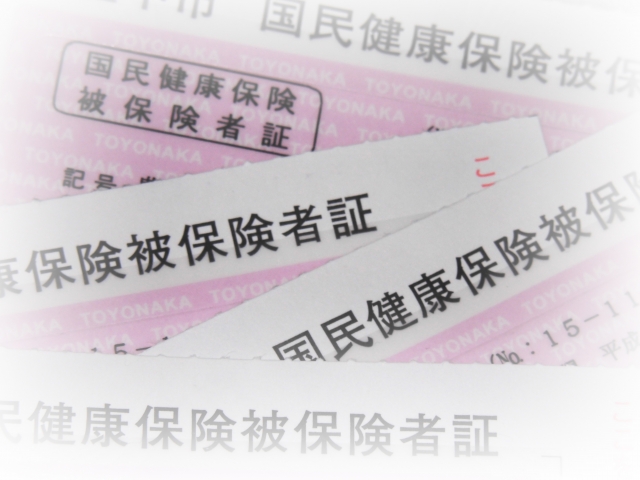 現在、国民健康保険は雇用保険の離職理由(会社都合など)により減免されることがあります。保険料は給与所得金額を3掛した額が基準に計算しますので、減免額はめちゃくちゃ大きいです
現在、国民健康保険は雇用保険の離職理由(会社都合など)により減免されることがあります。保険料は給与所得金額を3掛した額が基準に計算しますので、減免額はめちゃくちゃ大きいです
夫が退職した頃には離職理由による減免制度はありませんでした。もともと夫の退職理由は自己都合。離職理由による減免はないし、雇用保険自体も3ヶ月の給付制限がかかります。
実は、「病気にならんやろう」と長らく国民健康保険と国民年金を滞納していました。しかし雇用保険の受給が終わり、失業期間が長くなってきたので遡って払うことを決めました。
国民健康保険は失業の翌日が加入日となり、14日以内に加入手続きをすることになっています。今回は長らく滞納していたため、滞納分も含めて金額算定されました。
なんじゃ、この金額は
普通に払っていたら、それまでに払っていた金額の倍、おおよそ任意継続健康保険料位だったでしょう。
しかし、滞納していたので延滞金やらいろいろついて任意継続の倍以上の保険料になっていました。
国民健康保険の場合「個人で加入」ではなく、「世帯で加入」という捉え方をします。
- 所得割(世帯収入を元に決める)
- 均等割(世帯人数を元に決める)
- 平等割
という3要素を基準に保険料を計算します。
「私の所得を含められたらとてもじゃないけど払えません(T ^ T)。私は自分で健康保険に入ってるし、なんとかなりませんか?」
と訴えました。窓口の人は
「奥さんは人数には含めません。失業による減免についてはとりあえず申請書を出してください。通るかどうかはわかりませんが……。」
窓口の人は私の健康保険者証と夫の雇用保険受給資格者証のコピーを取り、私は申請書を提出しました。
後日3割の減免が認められたものの、失業世帯には厳しい額を払うことに変わりはありません。
結局一度も病院に行きませんでしたが、何かあってから遡って加入できないので加入しておいて良かったと思っています。
ちなみに、任意継続健康保険は会社の健康保険に引き続き入る制度です。退職してから20日以内に手続きしないとダメ。
健康保険料は会社と折半して払っていますので、退職後は会社が持っていた保険料を自分で収めることになります(上限あり)。保険料は2年間変わりません。
そもそも夫は会社と揉めて自己都合退職していたので、任意継続という選択はありませんでしたが……。
国民健康保険の場合、1年目の保険料は非常に高くても、2年目は所得が下がるので、保険料も下がる。
さ、どちらにするか……。
任意継続にされた方にお会いすることは少ないですね。
配偶者の扶養家族にする

夫が退職した時、「わたしの扶養家族にする」という選択肢もあり、会社に相談しました。
総務担当の方に「まだ若いし、すぐ仕事決まるだろうから扶養家族にしなくてもいいんじゃない?」と言われました。
手続きが面倒だったんでしょうね。
自己都合の給付制限中は扶養⇨雇用保険をもらい出したら扶養から外す(支給金額により扶養家族のままにする健保組合さんもあるようです)⇨支給が終わったら扶養家族にする」
という手続きを経るわけですから。
あと、男性を扶養家族にするのに抵抗あったのかな?
ちなみに
- 雇用保険基本手当「本格的に働きたいけど働けないから出る手当」
- 扶養に入る、老齢年金をもらう「本格的に働くのはちょっと…という時に利用する制度」
と支給根拠が真逆なので、完全に併給はできない仕組みになっています(65歳を越えると雇用保険と老齢年金の併給ができます)。
障害年金は「障害に由来して支給」されるものなので、併給が可能です。機会があれば障害年金についても書きたいと思っています。
夫が再就職した後飲み会でその話をすると、当時の所長代理が「男やから扶養認めんっておかしいな」。
この人が総務だったら我が家の家計は火の車にならなくて済んだのに……。
あ、配偶者の扶養のこと。「私は扶養に入れますか?」仕事でよく聞かれます。
「配偶者に、会社に聞くように促してください」と答えています。
うちもそうなんですが、手続きごとを嫌がる男性多いんですよね。でも、家のことなので配偶者に頑張って聞いてもらいましょう。
今回はここまで。次回は年金について書く予定にしています。
お読みいただきありがとうございます。